リチウムイオン電池の仕組みと火事の原因
電解液の可燃性
結論から言えば、リチウムイオン電池は中に入っている「電解液」が燃えやすい性質を持っているため、火事の危険があります。
理由は、この電解液が揮発しやすく、熱が加わると簡単に引火してしまうからです。実際に小さな火花や熱で燃え広がることがあります。
具体的には以下のような場合に危険性が高まります。
- 夏場の車内に放置して高温になる
- 電池に傷がつき内部で液が漏れる
- 過充電で発熱する
したがって「燃える液体が入っている」と理解して、取り扱いに細心の注意を払う必要があります。
過充電やショートによる熱暴走
リチウムイオン電池の火事の一番の原因は「熱暴走」と呼ばれる現象です。これは電池が異常に熱を持ち、発火まで進んでしまうことを指します。
なぜ起こるかというと、過充電やショート(プラスとマイナスが直接つながること)が引き金になります。すると電池内部で急速に化学反応が進み、温度が一気に上昇してしまいます。
危険な例を挙げると:
- 充電器に差しっぱなしで寝る
- 断線したケーブルを使い続ける
- ポケットの中で金属と接触させる
このような習慣を避ければ、多くの事故を防げます。つまり「熱を持たせない工夫」が重要なのです。
物理的な衝撃による破損
リチウムイオン電池は見た目よりもデリケートで、強い衝撃を受けると内部が壊れて火事になることがあります。
理由は、電池内部の仕切りが壊れてプラスとマイナスが直接触れ、ショートを引き起こすからです。
注意すべき行動は次のとおりです。
- スマホやモバイルバッテリーを落とす
- 電動キックボードの転倒
- 椅子や机で電池を強く押しつぶす
結論として、電池は「割れ物」と同じくらい大切に扱うべきです。普段から落とさないよう気をつけるだけで、火災の確率はぐっと下がります。
粗悪品(安価なバッテリー)のリスク
一番身近で見落としがちな危険は「安すぎるバッテリー」です。値段が極端に安い製品は、安全に必要な部品を省いていることが多いためです。
たとえば:
- 温度が上がると自動で止める回路がついていない
- 中の材料が不純で、劣化が早い
- 国の安全基準を満たしていない
こうした粗悪品は数回の使用で膨らんだり、発火する恐れがあります。ですから「安いからお得」と思っても、実際は火事のリスクを背負うことになるのです。信頼できるメーカー品を選ぶことが最も安全な選択といえます。
実際に報告されている事故例
家庭での火災例
実際にリチウムイオン電池が原因で家庭火災が起きています。消費者庁の発表では、充電中のモバイルバッテリーが発火して布団や机を燃やすケースが複数報告されています。
特徴的なのは「深夜に充電して寝ていたら火事になった」という例が多いことです。火がつくと煙が広がるまで気づきにくく、逃げ遅れる危険性もあります。
具体的に防ぐには:
- 就寝中の充電は避ける
- 可燃物のそばで充電しない
- 長年使った古い電池を放置しない
結論として「家庭こそ火事が起こりやすい場所」だと理解し、普段から対策することが大切です。
電動キックボードやスマホでの事故
近年増えているのが、電動キックボードやスマホでの発火事故です。移動中や外出先で起こるため、逃げ場がなく大きな被害につながります。
理由は、長時間の使用で電池が過熱しやすいことや、持ち運び中の衝撃で壊れることにあります。
事例の特徴としては:
- 駅や道路で突然煙を出す
- 充電中にキックボードが燃える
- スマホをズボンのポケットに入れていて発火する
これらは誰にでも起こり得る事故です。「屋外だから安心」と思わず、持ち運ぶ時こそ注意が必要です。
消費者庁や消防庁のデータを引用(信頼性UP)
数字を見ると、危険性の高さがよりはっきりします。消防庁の資料によれば、リチウムイオン電池が関係する火災は年々増えており、年間で数百件以上報告されています。
また、消費者庁もモバイルバッテリーの事故情報を公表しており、特に「安価な製品をネットで購入したケース」が目立っています。
このように、公的機関が具体的な数字で警告していることからも、火事は決して珍しい出来事ではありません。信頼できるデータを参考にすることで、個人の危機感も高まります。
火事を防ぐための正しい使い方
純正品やPSEマーク付きの製品を選ぶ
火事を防ぐ一番の方法は、信頼できる製品を選ぶことです。特に「PSEマーク」がついたバッテリーは国の基準を満たしている証拠になります。
純正品や認証を受けた製品なら、温度上昇を防ぐ仕組みが備わっているため、発火の可能性を大幅に下げられます。
選ぶ際のポイント:
- 正規の販売店から購入する
- 値段が極端に安すぎないか確認する
- パッケージにPSEマークがあるか確かめる
結論として「少し高くても安全を買う」と考えることが重要です。
充電しっぱなしにしない
リチウムイオン電池は満充電になっても充電器につないだままだと、内部に負担がかかります。これが熱暴走や劣化の原因です。
実際に「寝る前に充電して朝まで放置する」ことが火災につながる事例は多くあります。
対策として:
- 充電が終わったらすぐに外す
- タイマー機能のあるコンセントを使う
- そばに燃えるものを置かない
充電は短時間で区切ることが、電池の寿命を守ることにもつながります。
高温環境に放置しない
真夏の車内や直射日光の下は、電池にとって危険な環境です。高温になると電解液が膨張し、発火につながる可能性が高まります。
たとえば車のダッシュボードにモバイルバッテリーを置きっぱなしにすると、内部温度はすぐに70度を超えることもあります。
予防策は:
- 車内に置かない
- 炎天下のベランダに放置しない
- 高温になる場所を避けて保管する
「人が暑いと感じる場所は電池も危険」と考えると分かりやすいです。
水濡れ・落下に注意する
電池は水や強い衝撃に弱いため、それが直接の火災原因になることがあります。水分が内部に入るとショートが起き、落下で内部が壊れると発火に直結します。
日常で気をつけたい場面:
- 雨の日にポケットへ入れたまま外出する
- 洗面所や台所で水がかかる
- テーブルから落としてしまう
結論として、電池は「濡らさない・落とさない」が基本です。スマホやモバイルバッテリーを扱う時には、飲み物の近くや不安定な場所を避けましょう。
まとめ|便利さの裏にあるリスクを理解しよう
リチウムイオン電池は、スマートフォンやパソコン、電動機器など私たちの生活を大きく支えている存在です。しかし、その便利さの裏側には「熱暴走による発火」や「充電環境による火災」といったリスクが潜んでいます。事故の多くは、過充電や不適切な保管、粗悪品の使用といった「ちょっとした不注意」から発生しているのが実情です。
とはいえ、正しい知識を持ち、純正品や安全基準を満たした製品を選んで使えば、過度に怖がる必要はありません。大切なのは、便利さと危険性をきちんと理解し、日常の中で無理のない安全対策を取り入れることです。
次の記事では、このリチウムイオン電池を安全に活用できる「モバイルバッテリーの選び方」をご紹介します。外出先でも安心して使えるバッテリーを選ぶヒントになりますので、ぜひ続けてお読みください。
モバイルバッテリーの良さはこちらで解説↓
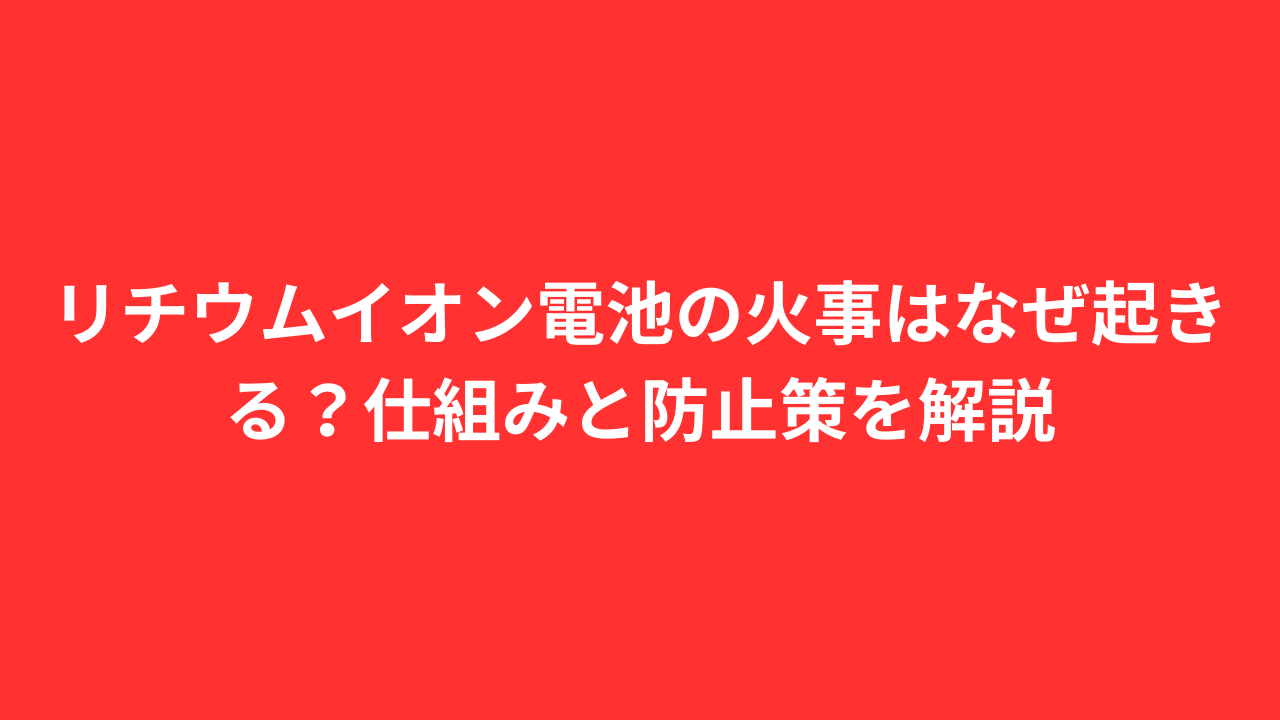
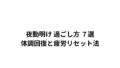
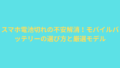
コメント